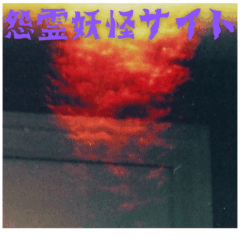「おまえはウラギリ者で~ございます! よっておまえは三日後には気が狂って死んでゆくのでございま~すッ!」
と、その「すッ!」という言葉と同時にその声の主らしき妖怪の親玉は私の左耳にへとばり付いた・・・
いったい、私が何を裏切ったというんだ、何が『オマエは三日後には気が狂って死んでゆくのでゴザイマスッ! 』だ! バカバカしい!・・・ いったい何がなんだか、全く訳がわからない。
という事は・・・「そうか、先月の、あの『十二がつ~十七、十八、十九にちは~大丈夫~で~ございます~』と、四六時中どこからともなく聞こえてきた、あのわらべ唄は私への『呪いの儀式』の予告だったのか!」
母も旅行に送り出し、自宅兼作業場であるスタジオにも予約は入っておらず、私一人となった三日間とは、絶好の私の発狂死、あるいは自殺に導く為の、バケモノ達の私の『死への儀式』の「御予約」だったのである。
・・・そしてさらにその大合唱は太鼓の拍子に合わせ、私の左耳元で延々と鳴り響いた・・・
「ドーン ドン ドーン・・・ドーン ドン ドーン・・・ 死んで~ゆくので~ございます~ おまえはウラギリ者で~ございます~ 三日後にはおまえは気が狂って~死んで~ゆくので~ございます~ドーン ドン ドーン・・・ドーン ドン ドーン・・・」
正直言って、こんなのを一晩中やられたら、いや、それこそ宣言通り三日三晩こんな大音量でやられた日にゃ、どんな図太い神経の持ち主でも、耐えられない・・・悪霊のいう通り、三日後には本当に発狂死か自殺、或いは衰弱死は免れられない・・・
そこで私は考えた
———-この聴覚さえ潰せば何とか命だけは助かるかもしれない—————-
と。
まさしくあの「耳なし芳一」的発想である。
今私が思うには、あの話の原型は地方に古くから伝わる昔話が元であり、という事は多分実話であったと推察する。
そして私も同じ悪霊らから受けた体験の上から仮説を立ててみるとする。
芳一の耳は悪霊が引きちぎったのではなく、私と同様、悪霊らの声に耐えきれず、実際に自ら切り落とした。
それに小泉八雲が物語としての創作を加え、一作品として現代に残っているのではないか、という事である。
さらに芳一は物語の中では「源平の墓に連れていかれた」という話だが、それはあり得ない。なぜならば源平の武士らの怨念は墓にはなく、後ほど話すがその霊は今だに関ヶ原に冥伏、つまり臨終の際の強い念が断ち切れず、地縛霊として今世に彷徨っているのである。
話を戻そう。その時の私は、
—————いっその事この耳を潰してこの聴覚がなくなれさえすれば、この大音量の悪霊らの声は聞こえなくなるのではないか・・・————————
と本気でそう考え、ドライバーか何かで両耳を突き刺し、鼓膜と中耳覚の機能を一気に潰して命だけは助かりたい、とも思った。しかし実際、そんな事をしても無駄である。
なぜならば、試しに耳をふさいでみても、その声と太鼓の大音量は頭の中心でガンガンと鳴り響いているのである。たとえ耳殻を切り落とそうが、聴覚の機能を潰そうが、全く効果はない事は明白であった。
———結局私にはどうする事も出来ないこの現実を受け入れたまま
一睡もすることも出来ず、呪いの儀式二日目の朝を迎えた—————-
私はもうろうとしながらも、何とかこの呪いの呪縛から逃れようと必死だった。そして誰にも気付かれないよう、レコーディングスタジオ内にこもり、ロックをして手には念珠をかけ、大声で「どうかどうか、お許し下さい、お許し下さい、せめて命だけはお助け下さい、妖怪様!」と泣きながらグルグルと延々歩き回っていたのである。
そのまま数時間が過ぎ夕刻になった頃、わずかではあったが私にもまだ冷静な判断力は残っていた。
そんな自らの行動を俯瞰で冷静にとらえ、自分自身がまさに「もしかしたら本当に気が狂っているのではないか?」と自覚したのである。しかしさらに容赦なく悪霊たちの大音声責めは続いた。 ついに、私は本当に気が狂い、
「あの、『三日後には気が狂って死んでいくのでございます』との悪霊らの宣言は本当の事だったんだ、三日間こんな状態が続けば発狂死、あるいは衰弱死、または自殺は免れられない。
「あぁっ、早く死にたいっ、苦しいっ、本当に命を絶ちたいっ・・・
この苦しみから逃れる事が出来るのなら・・・」
と本気で考えていた。
そして、
「明後日(呪いの儀式の四日後)には取引先が仕事でやってくる。母も旅行から帰ってくる、何としてでも、発狂死ではなく、せめて『過労死』という状態で死ななければ面目が立たない」
「どうせ死ぬのなら「発狂死」だけはごめんこうむりたい、そうだ!何とかしてせめて合掌し半眼半口の成仏の相で死にたい・・・」
と、悪霊達の思惑通り、まさに自殺願望にとりつかれた精神錯乱状態に追い詰められていったのである。
私はあお向けとなり、息を止め鼓動を止めようと必死に胸を押さえつけた。
「だめでございますっ!お前は我々を裏切った罪で、堕地獄の相で死んでゆくのでございますっ。よって左側を向き、目と口を固く閉じるのでございますっ!」
なるほど、確かに仏教典によれば横を向き、固く目と口を固く閉じた状態での死相というのは堕獄の相とある。
あのバケモノの宣言通り、二日目には私は本当に怨霊の思惑通り完全に気が狂いっていた。食事もせず、水分も一切取らず、トイレにも一度も行かず、家中を泣きわめきながら、グルグルとまわり続け確実に死への階段を登っていた・・・
————–こんな辛い思いを一生涯受け続けていくくらいなら、本気で死んでしまおうか、それともこの聴覚を突き潰せば命だけは助かるかもしれない、レコーディングエンジニアとしての仕事をあきらめ、一命だけは取り止めようかとの思いがまたよぎったのである・・・————————————————
しかし前日と同様、いくら両耳をさらに強くふさいでみたところでバケモノらの音声は頭の中心でガンガンと鳴り響く・・・
その日の二日目の深夜、私は泣き叫んでいた疲れで、意識はもうろうとし、完全に判断力を失っていた。
——-実際のところ、確かに視覚的には現実のすべての物体が見えている——
だが、ヤツラの姿は全く見えない。しかし精神的には怨霊たちのいる暗闇の音像の世界の中に入り込んでいる。そしてついに私は悪霊の意のままに行動するようになっていった。